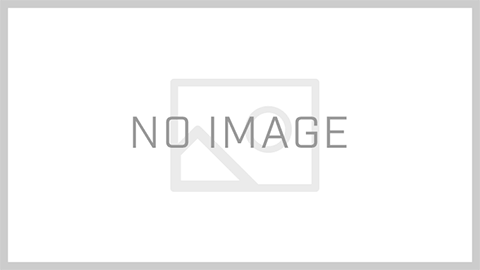子育ては前向きに【コロナ感染、自宅待機で気づいた子どもの成長】
自宅待機だからこそ見えてくるもの・・・
実は、今年で3回目となるコロナの陽性者が出てしまい、家族みんなで自宅待機をしています。
皆さんも家族の誰かがコロナウイルスに感染して自宅待機となり、子どもとの過ごし方に悩みながら、悶々とした日々を過ごしているのではないでしょうか。
少しずつ、待機期間が短くなっては来ましたが、発達障がいを持つ子どもと、限られたスペースしかない家でじっとしているのは、肉体的にも精神的にもなかなかツラい時もあります。
特に、子どもはコロナウイルス感染症の症状が無い時、家から出られないストレスがたまり、兄妹でケンカを始めたり、子どものYouTubeタイムが長くなるなど、このままで良いのかと不安になることもありました。
そんな生活でも、イライラや心配、不安なことだけではありませんでした。
少なからずですが、子ども向き合う時間が増えたからこそ気づけた、子どもの成長や気付きにも触れることができました。
私たちとしては、子どもが「こんな一面を見せてくれるようになったんだー」と感じる嬉しい出来事もありました。
今回は、そんな出来事をご紹介したいと思います。
甘えは自分を認めて欲しいサインかも…

息子は、男の子だから?個性?なのか分かりませんが、とにかく母親の私に甘えます。
お父さんとはならないようです(笑)
特に、この自宅待機期間は甘えっぱなしでしたね。
息子は、ご飯を食べる時も、おやつを食べる時も私の膝の上で食べたがります。普段からマイペースなので、皆で食事をとるタイミングで食べようとしません。
デイサービスに行く日であれば急かして食べさせたりしますが、自宅待機期間中は、時間の制限がないので、息子のペースに任せることで、私たち自身も、なるべくイライラしなくて済むよう心掛けていました。
そんな息子は、少し反抗期を迎え、私たちの言うことも聞いてくれない時もあり、内心としては心配になることも少なくありません。
例えば、息子は、アイスを食べる時、いつも新品のアイスを食べたいようです。
お腹がいっぱいになって食べたくない時は、もったいないので冷凍庫で保管しますが、次に食べるタイミングで、この残したアイスを出しても絶対に食べません。
こんなわがままで良いのか、いつも考えます。
私たちが子どもの時は、絶対に許されなかったことですし…。
息子は、極度の偏食で甘いモノはアイスしか食べません。
困ったことに糖分が不足すると、脱水症状となり病院で点滴コースになるのを何回も経験しているので、結局、糖分補給を優先させてしまい、新品のアイスを食べさせてしまいます。
それでも今回は、息子の敏感さも理解した上で、息子に話し掛けました。
「新しいアイスを開けても良いけど、世の中には食べたくても食べれない子もいるんだよ。少し我慢することも大切なことだよ」という内容を伝えてみました。
すると、息子は自分が残したアイスを食べると言い出しました!
残したアイスを完食し、もちろん新しいアイスにも手をつけるのですが、再び食べ残してしまう息子なのでした(笑)。
子どもが甘えてくる期間は大切なのかもしれません。そして「我慢すること」は、「甘え」の後に覚えていくのかもしれません。
実は苦手意識を持っている

発達障がい児の”あるある”かもしれませんが、息子は、自分より年下の子でもできるような遊びでも苦手だったりします。
我が家でも、妹にはできて、息子には出来ない遊びがありました。
よくある釣竿を使って魚が口を開けたら吊り上げる電池式のオモチャです。
娘が、そのオモチャで遊んでいる時、息子は関心なさそうにしていましたが、内心では自分ができないのが悔しかったようで、娘がお昼寝中に私を誘ってきて練習をしていました。
私は、息子が自分の苦手な事を克服する様子が見れて、すごく嬉しかったです。
そして、私が、息子のやりやすいように手を加えようとすると、「ママ、自分でちゃんとやってみる!」と言ってくれました。
『すごい!ちゃんとお兄ちゃんに成長している!』と、実感できた瞬間です。
もちろん、いつでも苦手を克服しようと努力するわけではありません。
「できないから、やりたくない!」とオモチャをぐちゃぐちゃにして逃げたり、他の遊びに移ることも少なくありません。
今回の息子の様子を見て、ちゃんと苦手意識を持っていて「出来るようになりたい」という気持ちもあることが分かりました。
無理強いをして、苦手なものを克服させようとする必要はないと思いますが、子どもの自主性を促して、親は見守りながら必要な時に手助けをするイメージで声を掛けてみると前向きになれるかもしれません。
苦手意識があるものには、無理に克服させようとせず子どもの気持ちを大事にして子どもからの行動を待つ姿勢で。
さいごに

子育てをしているとこれで良いのかなと考え、悩むことが沢山あると思います。
私も普段から、「甘え」と「甘やかす」の線引きが難しく、自分に問いかけをすることが多くあります。
それでも、基本的には、子どもと親が良い関係でいることが目標にあるので、出来るだけ子どもの側にいて一緒になって遊んだり、子どもとのコミュニケーションをとることを大事にしています。
息子の苦手意識へのアプローチとしては、息子自身が苦手意識を持っているものに対して、私たちに「手伝って欲しい」と言ってくれる関係を築くことが、子どもの苦手意識を軽減させることに繋がっていくように感じています。
これからも、大人になるまでの間、小さくとも多くの成功体験を積ませてあげられるように、焦らず、一歩ずつ、一緒に頑張っていきたいと思います。
小さくとも多くの成功体験を積ませることが、今後の子どもの生きる力になるような気がします。