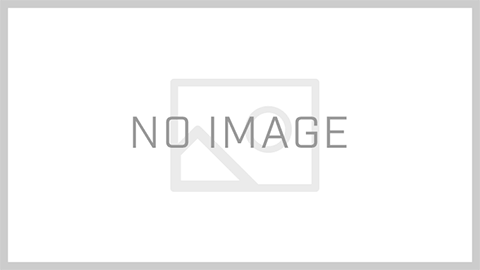5歳の発達障がい児へのコミュニケーションのコツ
日常会話のコツ

普段、お子さんと会話をしている時に、さっき、話した内容が伝わっていないのかな?って感じることはありませんか?我が家は度々あります。
娘は、記憶力が良く、覚えていることが多いのですが、息子は言葉で伝えても「ぽか~ん」としていることよくあります。たぶん、関心のないことや自分にとっては重要ではないと考えているのかもしれませんが、朝の準備や行事予定、デイサービスであった出来事などを聞いても返答がないことがあります。
ましてや、YouTubeを見ている時は、集中し過ぎているのか3~4回ぐらい話し掛けないと返事が返ってこないこともあります。そのことに、私はイライラしてしまいがちです。
その話を先生にしたところ、発達障がい児の傾向として、耳で情報を取り入れるよりは目で見て情報を取り入れる方が得意なので、YouTubeやテレビを真剣に見てしまいがちだと言っていました。
対策として、伝えたい事は長々と話すのではなく、なるべく短めに伝えると良いそうです。伝えたい内容を、すべて会話の中に入れてしまうと一方的な流れになってしまい、息子がどこまで理解しているのか分からなくなるからです。
また、途中から話を聞いてくれなくなった時は、「〇〇、ママの話をちゃんと聞いてる!」と怒らず、「さっきのことなんだけど~」というように、話を戻すようにして会話が続いていると気がつかせるようにしています。←難しい時もあります。
息子のデイサービスでは、朝の会に一日の流れが、目で見て理解できるように絵カードを使って説明しています。これは、視覚での情報を取り入れやすい発達障がいの特徴を取り入れたものだとも、デイサービスの先生が教えてくれました。
自宅では、スケジュールやルール、注意事項などは息子の視界に入るところに絵や文字で張り出すと良いと言っていました。なるほど!確かに、そういえば、息子は良くカレンダーや給食表を確認していますし、カレンダーを見ながら話をしてくることが多いです!
「じゃんけん」を教えることで再確認

毎朝、息子と娘はデイサービスに行く時に、なぜか競争が始まります。服を着たり、靴を履く準備が先にできた方が、本人たちの中では勝ちみたいです。
息子と娘は、2歳差で良いライバルなのですが、2人とも成長がどっこいどっこいで私が急かされて慌てる状態です(笑)。
娘は、靴下が上手に履けず、息子はジャンパーのチャックで悪戦苦闘します。時には、上手にできずに2人とも泣き出すこともあります。親としては競争なんてしなければ良いのにと思ってしまいますが…。
これは「一番病」と言うらしく、自己肯定感の低い子どものあるある話と先生が教えてくれました。そんな話を聞くと、根気強く向き合っていくしかないと考えるようになります。
それでも、少しずつ息子は、ジャンパーのチャックのコツが分かってきているようですし、娘も冷静な時は、自分で靴下を履く努力をしてくれるようになりました。
そんなこんなで、朝の支度は2人の状況に合わせて双方の手伝いをしています。どちらにも手伝いますが、やはり3歳の娘を優先的に身なりを整えていることが多いです。
結局、同じぐらいのタイミングで準備が終わるので、次は誰が先に玄関のドアを開けて外に出るかでケンカが発生します。その時に「“じゃんけん”で決めたら?」と提案します。それは、息子が”じゃんけん”を理解していないからです。
5歳なら、そろそろ“じゃんけん”を理解しても良い時期だと思うで、2人で“じゃんけん”をさせたり、「ママに勝ったら先に外に出られるよ。」と話します。そこで問題になるのが、じゃんけんのグー・チョキ・パーの手の形はできるのに、どちらが勝ったのか分からないことです。私は、子どもに口で”じゃんけん”の説明をします。
例えば、グーはね、石だと思ってね、チョキはハサミだよ。そしたら、グーの石が硬いから、チョキのハサミは切れないよね?だから、グーが勝ちなんだよ。」というような感じです。
息子に、ある程度説明した後にどちらが勝つか、もう一度、質問してみます。すると、私の言葉を単純に繰り返すだけで、内容を理解していないことが分かりました。その後、手を使って説明すると少し理解できている様子でした。
説明する時は、短めに視覚からの情報を入れると理解しやすいようです。抽象的な説明や、何かをイメージした説明は頭に入らないみたいです。長い時間をとって説明して、自分が理解できないと分かると、すぐ、自分の関心の話へと切替えられます。また、苦手意識を持たれやすくなるので、今日は難しいかなと思ったら、「また今度説明するね」と切り上げた方が説明を聞いてくれるようになります。
根気強く

年長ともなると、日常会話もできるようになり、言葉の理解がどんどん進んでいると思って、子どもに沢山の情報や物事の説明をすることが多くなりますが、一方的になりがちだったりする時もあります。
私の場合は、子どもの事が心配で色々と知識や考え方などを伝えたくて、まだ子どもが理解できないことも話をしてしまっている時があり、主人からまだ早いんじゃないの、と注意を受けることもあります。
大切なことは、根気強く向き合うことなのかもしれません。なんで、伝わっていないんだろうと、イライラすることもあるかと思います。でも、親がイライラしていると、子どもは視覚からの情報を取り入れやすいので、ママの怒っている顔しか残りません。いつか、分かってくれる時がくると思って、何度も説明するようにしています。その方が、結果的に良い方向に向いていっているように感じます。
大切な事は、出来る範囲で言葉だけでなく絵を描いたり、動画や教材を利用して子どもの理解に繋げる方が良いようです。私が気を付けていることは、なるべく怒らずに繰り返し伝え、本人のペースを守ることを意識するようにしています。
人生は、多くの方が大人として生きる時間が長くなるので、親子で過ごす時間を考えれば、穏やかでいられる方がお互いの人生にとって良いですよねと、最近買った「COFIL(コフィル)」で入れたコーヒーを飲みながらホッと一息をつきながら思い返す毎日です。
↑雑味が無くなります。最近のイチオシです。